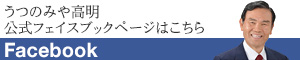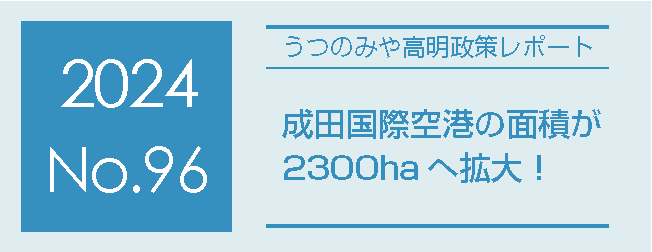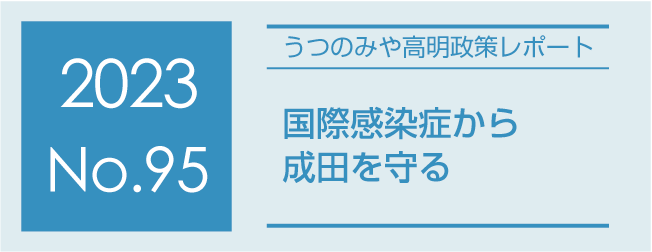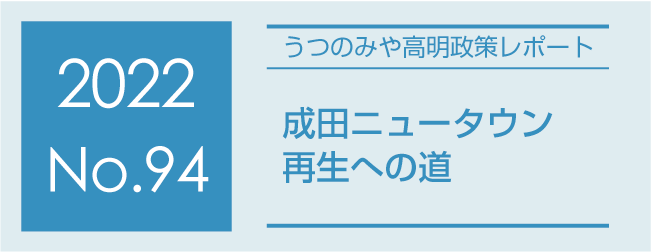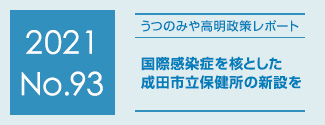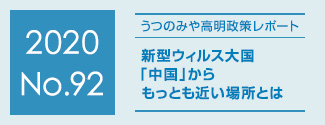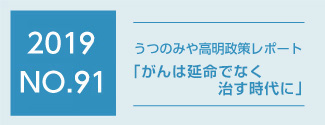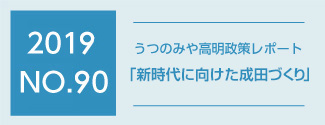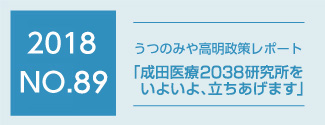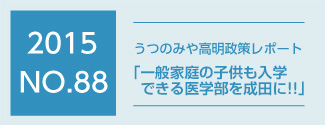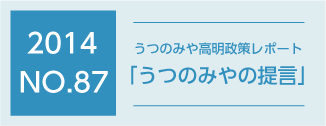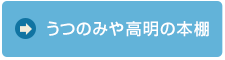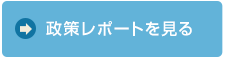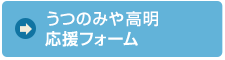モバイルトップページ
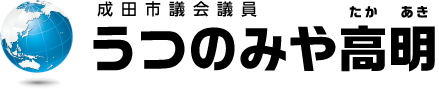
うつのみや高明の本棚
■「信頼の貯蓄」
■「北風は太陽に負けない!」
■「全体の中で生きる個」
■「感謝にまさる能力なし」
■「ゆく河の流れは絶えずして」
■「食足りて礼節を知る」
■「子曰く」
■「満は損を招き…」
■「中道を行く!」
■「一隅を照らす」
■「地球に生かされている!!」
■「人生は心ひとつのおきどころ」
■「美しい地球を子供たちに」
■「1492年、コロンブス新大陸発見の見方・考え方‼」
■「成田の地に、空港決定から半世紀‼」
■「徳の貯蓄 -修養:新渡戸稲造著-」
■「この大地は祖先から譲りうけたのではなく、子孫から借り受けているものである
(ネイティブアメリカンのおしえ)」
■「自反尽己(じはんじんこ)」
■「苦難にまさる教師なし」
■「十年樹木・百年樹人」
■「百萬経典・日下之燈」
■「一に国語、二に国語、三、四がなくて五に算数、あとは十以下」![]()
統一地方選を『自分事』に
~投票はまちづくりの第一歩~
 4月には統一地方選挙があります。日本中で首長や議員が選ばれるのです。
4月には統一地方選挙があります。日本中で首長や議員が選ばれるのです。
しかし投票率は昭和26年の約9割から前回の約5割まで低下し続けています。
つまり、私たちは地方自治を60年間にわたって「他人事」にし続けてきたのです。
実は市長や町長、地方議員などの権限は大きく、国会議員よりも私たちの生活に大きい影響を持っています。「他人事」の結果は地方政治・行政の劣化。ツケは自分たちに回ってきます。
これをどうやって「自分事」にしていくか。私も長い間、参加させていただいている「構想日本」の声です。
「21世紀に生きる君たちへ」
司馬遼太郎
 さて、君たち自身のことである。君たちはいつの時代でもそうであったように、自己を確立せねばならない。…自分に厳しく、相手にはやさしく。という自己を。そして、すなおでかしこい自己を。21世紀においては、特にそのことが重要である。21世紀にあっては、科学と技術がもっと発達するだろう。科学・技術がこう水のように人間をのみこんでしまってはならない。川の水を正しく流すように、君たちのしっかりした自己が科学と技術を支配し、よい方向に持っていってほしいのである。
さて、君たち自身のことである。君たちはいつの時代でもそうであったように、自己を確立せねばならない。…自分に厳しく、相手にはやさしく。という自己を。そして、すなおでかしこい自己を。21世紀においては、特にそのことが重要である。21世紀にあっては、科学と技術がもっと発達するだろう。科学・技術がこう水のように人間をのみこんでしまってはならない。川の水を正しく流すように、君たちのしっかりした自己が科学と技術を支配し、よい方向に持っていってほしいのである。
上において、私は「自己」ということをしきりに言った。自己といっても、自己中心におちいってはならない。人間は、助け合って生きているのである。私は、人という文字を見るとき、しばしば感動する。斜めの画が互いに支えあって、構成されているのである。そのことでも分かるように、人間は、社会をつくって生きている。社会とは、支え合う仕組みということである。原始時代の社会は小さかった。家族を中心とした社会だった。それがしだいに大きな社会になり、今は、国家と世界という社会をつくりたがいに助け合いながら生きているのである。
自然物としての人間は、決して孤立して生きられるようにはつくられていない。このため、助け合う、ということが、人間にとって、大きな道徳になっている。助け合うという気持ちや行動のもとのもとは、いたわりという感情である。他人の痛みを感じることと言ってもいい。やさしさと言いかえてもいい。「いたわり」「他人の痛みを感じとること」「やさしさ」みな似たようなことばである。この三つの言葉は、もともと一つの根から出ているのである。根といっても、本能ではない。だから、私たちは訓練をしてそれを身につけねばならないのである。その訓練とは、簡単なことである。例えば、友達がころぶ。ああ痛かったろうな、と感じる気持ちを、その都度自分の中でつくりあげていきさえすればいい。この根っこの感情が、自己の中でしっかり根づいていけば、他民族へのいたわりという気持ちもわき出てくる。
※この記事は『21世紀に生きる君たちへ』司馬遼太郎さんのメッセージより抜粋したものです